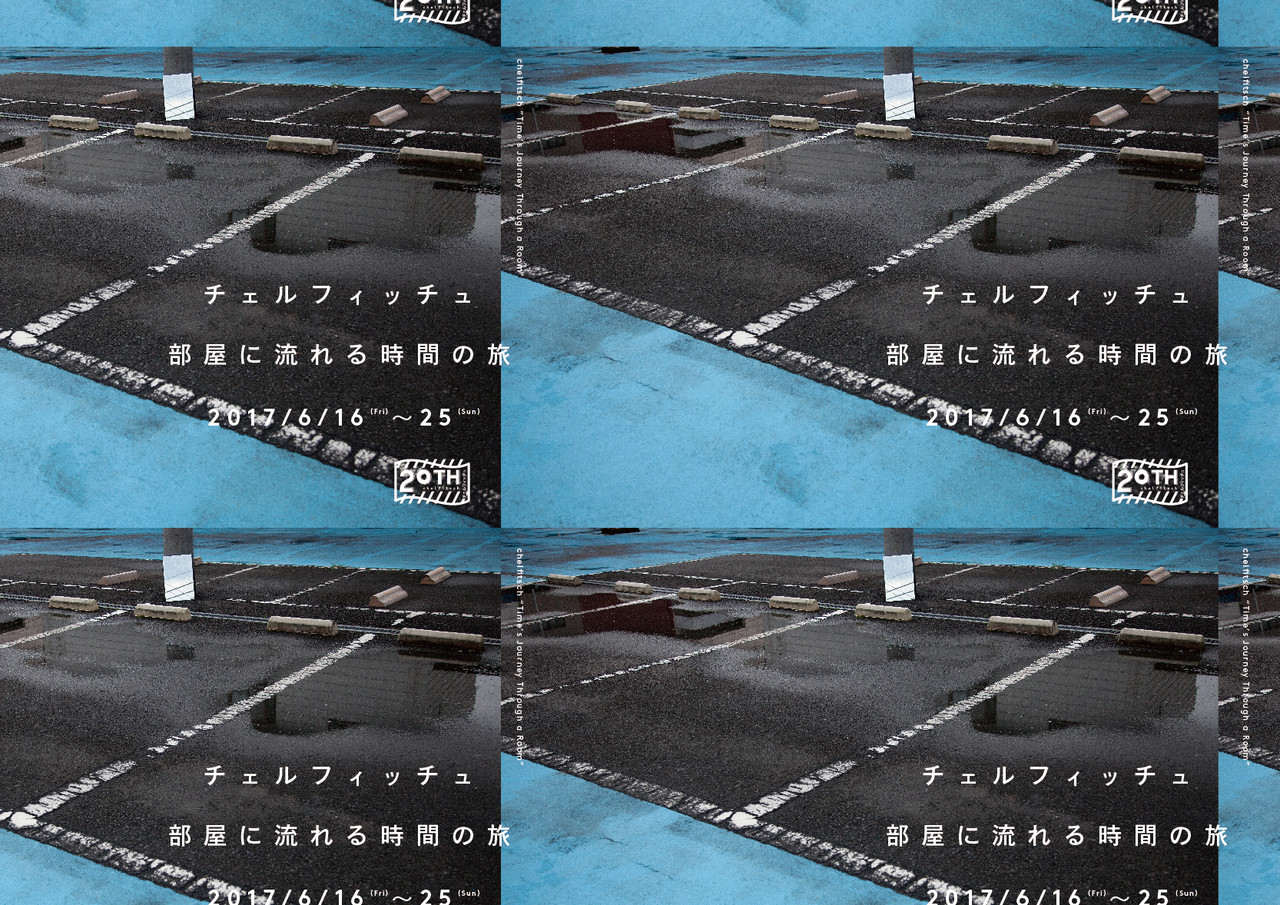【映画】マンチェスター・バイ・ザ・シー
曇り空の港町の風景。
志が高いのか低いのか計りかねる、灰色の景色。
映像のトーンもこの時点では決して上質とはいえない。
そんな風に映画ははじまる。
景色は寒々しいマンチェスター港から雪景色のボストンへ。
これはアメリカのマンチェスターの話。
そしてボストンで雪かきをする陰気な男がスクリーンに現れる。
男の名はリーという。
観終わって、とても余韻が長く尾をひく映画だった。
なぜだろう。
地味な、とても地味な映画だ。
ドラマはある。強くあるのだけど、ことごとく沸点となる描写を回避している。
全てが日常の、灰色の街の景色の中に落とし込まれている。
主人公のリーは訳あって故郷を離れ、ボストンでアパートの便利屋をやっている。人望厚く皆に愛された兄が心不全で亡くなり、遺された高校生の甥・パトリックの面倒を見るため一時休職して故郷に戻るリー。なぜリーは故郷を離れたのか。パトリックの面倒は誰が見るのか。兄の遺言は。ゆっくりとストーリーは進んでいく。
リーはあまりにも不器用で寡黙だ。口も悪い。なぜそうなったかの理由も作中で語られるわけだが、なんであれこんな中年が近所にいたらいい気はしない。実際、リーは職場でのウケも最悪だし、本人もそれを悪びれる様子がない。そんな男が主人公な時点で特にロクなことが起こるはずもないし、実際起きない。どこにでもありそうな中途半端な不幸と中途半端な日常の描写がつぶさに続いていく。
中途半端な不幸、中途半端な日常。
作中で語られる「ある不幸」は中途半端とは言えないエピソードだ。
ただ、この作品の中で流れる時間は常に何かが「うまく行かない」。
いつも余計な何かがそこには起こって、
完全にシリアスな状況にも、完全にハッピーな状況になることもない。
人々はいつだって目の前のそれに対応するのに手一杯だ。
リーは一人残された甥のパトリックの後見人になるという突然の役割を、陰気な独り言を呟きながらもとりあえず全うする。遺産となる船はどうするか。家は。遺産は。一つ一つ道筋をつけていく。これからパトリックの進んでいくだろう道と、進むべき道をとうに失っているリー。二人の境遇がじょじょに重なって見えてくる。
大なり小なり、毎日起きる「余計なこと」。
これがなければ完璧だったのに!なんて日はいくつもある。
でもそれがなくなる日はないし、
完璧みたいな不幸な日にもそれは起こる。
ならば人生ってのは、その「余計なこと」の方にあるのかもしれない。
「余計なこと」の前では私たちは苦笑いすることしかできない。
苦笑いして、やれやれと重い体を持ち上げて今日も歩いていく。
鑑賞後、銀座の街を行く人々を眺める。
みんな生きて、それぞれに苦笑いしている。
結構なことじゃないか。歩いていくとするか。
【舞台】チェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』
おそろしい完成度のものを観た。
チェルフィッチュの新作公演。
観たのは「God Bless Baseball」以来だから、約2年ぶりになるだろうか。
僕も過去作の「三月の5日間」で思いっきり衝撃を受けた多くの人間のうちの一人なので、その後もチェルフィッチュの作品にはできる限り足を運ぶようにしていた。
ただ「三月の5日間」が方法論としてあまりにも「出来上がって」いたせいか、その後に続く作品たちにはどこか飛び抜けた印象を感じられずにいた。単に好きすぎて期待を大きく持ちすぎていたからかもしれない。そういうことはよくある。加えてここ最近は極端に席数の少ない変則的な公演が続いていたのでしばらく足が遠のいていたのだけど、今回は久々にチケットを取ることができた。
今回の作品、東京公演は三軒茶屋のシアター・トラムでの上演。
劇場に入ると、舞台上にはすでに照明が当たっていて、そこに並ぶ美術が目に入る。
テーブルと二脚の椅子。その上に水の入ったグラス。
舞台奥にカーテン。風に揺れている。
そして手前には…なんだろう?
小さなドラム缶?のようなもの。
中は空洞で、ときおり内側がふわりと光るのが見える。
その手前でレコードプレイヤーのように回転する円盤状のもの。
その上に石が乗っている。石。なんの変哲もない石。回転。
配置された一つ一つのものは当たり前のものなのに、
舞台上のその光景はすでに何かがおかしい。
気づけば劇場内にはうっすらとノイズ音が流れていて、
ほのかにうごめく美術はそのノイズに共鳴しているようにも見える。
舞台にはまだ誰もいない。
誰もいないが、何かの気配だけがある。ものが生む気配。
チェルフィッチュといえば独特な「しぐさ」の演出が特徴とされるが、ある意味今回はその演出を美術にまで拡張したということかもしれない。そしてその企ては高い精度で成功していたと思う。
作品群を見ると、彼の作品のいくつかがそのまま採用されているようだ。
美術と音の醸す静謐な緊張感の中、冒頭しばらく椅子に座ったまま背中だけを見せ続ける男。まるでどこか宇宙空間を浮遊しているかのように手足を空間に揺らしている。流れるノイズ音との間に規則性があるようでないような、うごめくモノたちと対応するようなしぐさ。人とモノの境目が曖昧になる。
一方で対となる女性の演者のしぐさはそこまで誇張されない。ただ、テーブルをなぞる手、水の入ったグラス越しに歪んで見える赤いマニキュア…舞台上のそんなディテールがはっきり記憶に残るほど、極めて「緻密」だ。
本作のテーマははっきりと「不在」だ。
「不在」をどう受け止めるか。「不在」とどう向き合うか。
「不在と向き合う」とはおかしな話だ。
だってそれはそこにいないのだから。
それでも向き合わなければならないのだとしたら、「不在」の側にそこに現れてもらわなければならない。
本作の美術、音響、演技、セリフ、そのそれぞれによる極めて緻密な「異和」の創出は、全てその「不在をそこに現す」ための儀礼だったかのように思える。それを必要とするものによる切実な、そのためだけの儀礼。それによって「不在」がこちら側に現れたのか、私たちが「不在」の側に引き寄せられたのか、それはわからない。
本作の冒頭で、客席に向かって語られるなんて事のない一言。
"PLEASE OPEN YOUR EYES."
目は開かれたのか、ただ閉じていたことに気づいただけか。
いまこれを書いていてもう一度それを反芻している。
A君のこと
Instagramにアップされていたある写真が目に止まる。
ドイツの古い農具の写真。
それを見て、古い友人のことを思い出した。

https://www.instagram.com/p/BWacZEYlEns/?taken-by=nshimu
続きを読む
旅と物語とことばについて
バカンスに来ています。

旅先の宿に書棚があり、ふと目についた背表紙を手にとってパラパラと読む。普段なら読まなかったであろうその物語が不思議なほどするすると喉元を通っていく。景色がクリアになるような体験。某有名女流作家の作品で、有名すぎて逆に手を伸ばし損ねていた、という感じの作家の本でした。
それはある旅をモチーフにした物語で。
ふだん旅ってそれほどしない(好きだけどなかなかできない)のですが、飛行機に乗りフェリーに乗って宿につき、「あ、今旅してるな」と気づいたのは、その場所の静寂に気づいた瞬間でした。鳥の声。凪いだ風。それだけ。
これは雑記なので話は飛びます。
以前、朗読会というものを催しました。
読み手は僕と、友人のなっちゃん。
お客さんの前で、小説やら何やら、いろいろなテキストを朗読する。お客さんはそれを、美味しい日本酒を飲みながらゆるりと聴いている。テキストとテキストの合間にはそれらの物語をうっすらとつなぐようなおしゃべりがあり。そんなざっくりとしたイベントでした。
その時に何を朗読するか、本を選んでいて。読んでみたいものはいくらでもあるのですぐ決まるだろうと思っていたら、思いの外苦戦。声に出して読むことがしっくりくる本と、そうでない本というのがはっきりとあるのです。好き嫌いには全く関係なく。とても好きな良い本でも、ものによっては音だけで読んでいると意味すらわからなくなる、というものまであるほど。
たまたまかもしれませんが、結果的にそのとき選に残った本は、そのほとんどが女流作家の作品たちでした。そのことに気づいたときはなんだかすごく不思議で、だけどどこか当たり前のことでもあるかのような、名前のつけがたい納得感を抱いたものでした。
女性の扱う言葉。
男性の扱う言葉。
それは同じもののようでいて、全く異なる文法を持ったものだ。そんな話をよく聞きます。自分なりに解釈すれば、男性にとって言葉は論理を組み立てるための部品であり工具みたいなもの。それは実感として理解できます。
一方女性にとっての言葉は ー それはあくまでそのとき手に取った女流作家の傾向からの類推でしかないですが ー お互いのコミュニケーションのためにひとつずつ手渡す小さなギフトのような、そんなものなんじゃないか、という気がします。
朗読したときに口から飛び出るものがゴツゴツした工具であるより、ふわふわしたリボンに包まれたギフトボックスのほうが受け止めやすいですよね。男は工具でカチンカチンやり合うのも好きだけどさ。テーブルの周りに開かれた小さなギフトボックスがたくさん並んでいる。ギフトそのものも大事だけど、その光景を相手とともに眺めることがそれと同じくらい大事、というような。そして朗読にはそんな景色のほうが向いているようです。
その宿で手にした本の主人公は、旅先で「信じられないようなあざやかな黄色の肌をもつ鮫を目にした」ことから、閉ざされていた箱を次々に開けていくように、いろんな気づきを得ていきます。たとえば、「自分が本当にいたいと思う場所は」というような、生き方の根本に関わるような問いに対する気づきを。
もっといえばそれは、答えを得てはじめて問いそのものの存在に気づくような体験です。
僕が旅に来て旅に気づいたのは、その静寂に気づいたときと書きました。
静寂には、言葉がありません。
男性の言葉が工具だとすれば、それはすでに「あるもの」を使って「まだここにはないあたらしいもの」を永遠に組み上げ続けるようなものかもしれない。一方女性の言葉とは、僕が感じた静寂についての気づきのように、渡されたギフトを開くことで「そこにはなかったはずなのに、ずっと前からそこにあったもの」を気付かせるような、そんな意味を持つもの。常になにか、言葉によって言葉の外側を指し示す機能を持つものであるような気が、いつもしています。
いつかここで手にした本と、それを旅先で読んだ自分のこの心模様を両方織り交ぜて、また朗読というとても素朴で小さなイベントの場に持っていけたらいいなあ。
もう少し旅してきます。
そして静寂が訪れる。
「典型的で凡庸な不幸」を生きるということ
ポストバブル時代によく語られていた「高度経済成長で人間は何かを失っていないか」的な問いや学歴主義批判。ドラマや何かでは、「エリートだけど不幸」という人物像が頻繁に、否定的に描かれていた。あまりにも繰り返し語られるので、そんなベタな人物が本当に実在するのかとずっと不思議に思っていたものだ。
社会はずっとそうした人物に好奇の目を向けていたと思う。ドラマ「ずっとあなたが好きだった」の冬彦。東電OL殺害事件の被害者女性。それをベースにした桐野夏生の小説。他にも色々。
エリートの不幸、エリートの転落。エリートでない我々はそういう話が大好物だ。嫉妬の裏返しとしてだけでなく、そこには人を惹きつけるものがあるんだろう。人の根源を垣間見るような何かが。そう思っていた。
このFacebookのノートに書かれた、とある女性と現在国会議員となり最近問題を起こしたある人物とのバブル期の青春の回想録は、上記のような人間の謎だったはずの部分を、手品のタネを全てテーブルの上にばら撒くような調子で軽々と人目に晒してしまっている。
高圧的な父親、従属的な母、罵倒する兄、他人の評価の中でしか生きられない自分と、その結果として異性からの性的評価を強く求める傾向、など。語られる内容はある意味前述の作品や事件ルポよりもリアルだし、端的だ。
これを読んで深くため息をつきたくなるのは、そこで語られることが人間の深淵に触れる何かだからなのではない。むしろその浅薄さに圧倒される。全てがあまりにも「想像通りすぎる」。深い闇に見えたその物体は、触ってみたらただの古ぼけた風呂敷で、おそるおそる開いたところで大したものは入っていなかった。陽の光に晒されたそれらの謎は、ひとつひとつ本当に陳腐に見える。
学歴や成功と人の幸福に相関がないなんて当たり前のことを、一体我々は何度問いなおせばいいんだろう。上を目指したければ目指せばいい。そうしないのだって人の勝手だ。ただそれだけのこと。それをどうしても受け入れられない、受け入れては生きていけない魂が、まだこの国にはあちこちに大量に浮遊している。まるで墓場の人魂みたいに。
テンテンコ 「Good bye,Good girl 」(MV) - YouTube